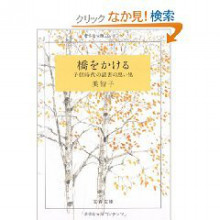金曜ロードショー『崖の上の上のポニョ』のTVデビューの視聴率は29.8%だったそうです。
たくさんの人が見たんですね。
同日、政府が出した自殺予防対策緊急プランより、ポニョの緊急デビューのほうが、絶望する人々を引き止める力があると思います。
『崖の上のポニョ』のストーリは…
海沿いの崖の上に住む5歳の少年宗介が、さかなの子ポニョと出会い、心を通わせる物語です。
ポニョは家出しようとしますが、一度は成功しても、すぐ父フジモトに海へと連れ戻されてしまったりして容易ではありません。でもあきらめないでいると、「魔法」が使えるようになって、願いが叶いました。
変わりたいと思っている人にとって、心を通わせることのできる存在は貴重です。
心理学ではラポートと言います。心と心に橋をかけるんですね。
安心して思ったことが話せる関係を意味しています。
これがありそうでなかなかないのです。
PTSDに苦しむ人たちへの支援には宗介のような素直な存在が不可欠です。
要するに何も難しいことではなく、相手の言っていることを否認したり否定したり無視したりするのではなく【傾聴】することですから、実は5歳の子どもでもできることなんです。
続きを読む