視聴率を稼ぎたければ
PTSD風が
お約束です。
わが国のかくれた
焦眉のメインテーマ ←眉の濃いマツジュン
だから
当然です。
マツジュンは
親の七光りと揶揄される
コンプレックスの持ち主
―臨床心理学のジュニアは
発達障害に逃げた?
(この時期この言葉使うだけで
恥ずかしいコト )
)
スカイダイビングで
落下
木の枝にひっかっかり
予想もしなかった手段で
助かり
ある女性にひとめぼれ します。
します。
【如人千尺懸崖上樹】 ←木の枝にかじりつく人
ポニョ 崖の上の
マツジュン 木の枝の
これは別名
【百尺竿頭一歩すすめよ】
禅のリセットの法則ですが
高いところから落下するような
危険を冒す人こそが
思いがけない
救いと
自分の目(ものの見方)を
捉えることができる という
という
ことです。
禅は生きた哲学です。
PTSD克服は
これしか方法が
ありません。
続きを読む



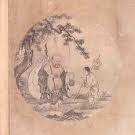


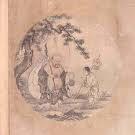




 みたいなガラスの
みたいなガラスの みたいな。
みたいな。



