大きな仏さまということで
よく照らすので
光は意識
こころがひろいというイメージのようです。
これが全部見える
昔の人が
往生際に
阿弥陀仏 の名を唱えたことから
おだぶつは
象徴的には
死ぬことで
それに準じることを意味するようになりました。
物や事がダメになること
あるいは失敗に終わること
物が壊れることは
お釈迦になるとも言いますね。
よくご無事で…
医療保護入院的な留置で落ち着き
警察の分析では原因は向精神薬ではないかと
― 医療過誤ですか?
やはり覚せい剤と変わらないんですね。
死と再生ということで
魂の死は
悪いことではありませんが
かなり恐ろしく感じるようです。
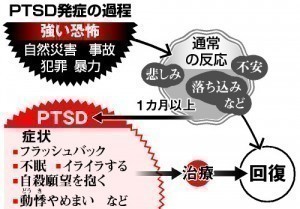
死の恐怖ですからね。
それで奇行となってしまったようです。
― 解離行動


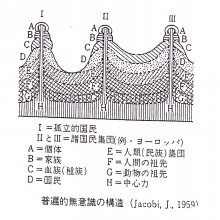

覚醒剤とかは経験がありませんが、向精神薬のベンラファキシンは経験があります。
2017年以来、向精神薬の副作用や後遺症ばかりに注目が集まっていましたが、向精神薬の効能も細かく観察する必要があると私は感じています。決して、薬服用を勧めているのではなく、薬を中枢神経に入れてあげる事でどの様なマインドステートになるかを治療者は知っておくべきだと思います。
で、ベンラファキシンを飲んでいる時の私。集中力アップ⤴️。その状況で良い行動でも悪い行動でも見境無しに集中できます。ヒプノ界隈言葉で言えば、意識が全て潜在意識でうまってしまったかの様にブリリアントなマインドステート❤️潜在意識優勢なので身体がそこについて行こうと凄い一生懸命になれます。身体(行動)が潜在意識と合致してしまうと物凄いパワーが出てくるんですね。そういう状態にさせてしまうベンラファキシンの良い部分と悪い部分をスキーをしている最中に同時に経験したドラゴン🐲です。
何だか、言葉のサラダっぽい文章ですみません。今、個人のマインドステートと集団のそれとの相互作用のエッセイ書いてるので頭の中メチャクチャ状態。イッチャッテルw。
それは覚せい剤経験者の報告と同じですよ(^^♪
勉強や仕事(単純作業)の効率を上げるためにコカインやリタリンなどを使用する人たちのことも、以前から欧米を中心に問題視されています。
苦行僧(断眠・断食)のように集中可能です。
瞑想のように有益な気づきが起きるものでもない空しいもの(+虚脱感で依存症一直線)で、ヒッピーだとサイケデリックアートになってしまうけど、某国のある時代の大ヒット曲はある程度才能のある人たちによる覚せい剤音楽だと言われていますよね。
S先生はある程度考える力を残したまま(だから苦しい治療になる)効能?として使っているとご主張です。
S先生には悪いけど、薬が中枢神経に入ると、たとえ少量でも思考能力は飲んでいない時(断薬して離脱症状が出なくなっている状態)と比較して段違いで衰えてしまいます。中途半端な量のお薬が脳🧠に入っている時の方がむしろ多大なストレス(賦活症候群)を引き起こすリスクがあると感じています。S先生の患者は、皆さま少量の薬で思考展開バンバンされていたのでしょうか?私は、離脱症状発症中は人の話し言葉を理解解釈する事さえも困難で思考停止状態でしたよ。余計に解離が進んでしまった様な状態になっていた記憶があります。エレノアロンデンも、確か、薬が思考展開の邪魔をするから早く薬を辞める(脳内から薬を除去する)事に必死だったと語っていましたよね。
やっぱり、薬の経験がないとその体感と思考が結び付かないのかもしれませんね。臨床に居れば、そこら辺に気がついても良いと思うのですが、そうでは無い事にビックリ❗️フィードバックループ🔁が全く無い臨床って、意味無いじゃん❗️
普通に考えてまあそうですよね。
催眠にかかることをよしとされていて、思考展開バンバンという発想はないのです。
抑圧しているものが浮き上がってきて思い出す(そして再度抑圧しない)ことができる程度の思考能力というか自我のコントロール能力でよいのでしょうが、それがキツイ作業なのだそうです。
その通りです。
薬飲んでると、自我バランスを元来のequilibrium 状態にする事が出来ないのですよ。
S先生って、ホントに精神分析を学んだ先生なのかな?って感じてしまいます。
時代的に、精神分析医以外は独学ですからね(^^♪
そっか。精神分析を独自で学ぶと偏った学びになるというのを何処かで聞いた事が…..
それに精神分析学そのものの前提は、あくまでも欧州白人思考なので、それを日本のオーソドックス(薬物療法)な精神科医が自身の治療に適用しても、単なる部分的サル真似解析🧐で終了してしまうと…..即ち、精神分析理論を簡略化してしまうリスクが大幅アップ⤴️という事になる訳ですね。簡略化すると何が起きるか….そうですね。正にS先生を教祖化してしまったameblo現象が起きた事はしっかりと記憶に残っております。オーソドックスな精神科医をSNSで教祖化してしまった現象は、今回の論文の第1章で書かせて頂きました。精神分析を臨床外で部分的に使用するリスク….いやいや、思い出すだけでも凄いものがありましたね。
すいません。昔の事を引っ張りだして..多分、翠雨先生も夏の準備でお忙しいですよね。私も金曜日から4日間籠って書きます。締め切りは今月末です….間に合うかなぁ。あゝ、日曜日には次男がお昼食べに来るけど、ケータリングで済まそうとするアコギな母でございます。
そんな感じだと思います。
あれはあれで化石のような1つの一大症例群(内部にたくさんの症例を含む)でした。
思い出すたびにすごいことが起きていたのだと認識を新たにします。
そして改めて浮かび上がるのが教育分析の大切さです。
薬の方は自分が経験するわけにはいかないのですが、なぜかこちらだけ通過(経験とはなっていない)した人が少なくなくて。
これもある種の根源的なアパシー(正業だけ率先してやらない)ですね。
昨日は投稿中に直前の作業を忘れアレっ(・・?と思ったら、一瞬寝ていたことに気づき驚愕しました💦
魚を捌いたりしながら現実感覚と遊離しないように気をつけ始めている今日この頃です。
ヒントをくださってありがとうございます♪
「教育分析の大切さ」
これをクリニック外で精神分析を使用する際に生じる問題である「理論の簡略化」の防止の為に分析家に必要な事として書きます。確かにそうですね。Foehl(2010)が指摘する様に、精神分析の本質は理論的枠組みだけでは無く、分析的出会いの瞬間性にもある…と言う様に、その瞬間で効果的な分析をする為にも、研究者や実践家は、自らの理論的前提を常に批判的に検討する姿勢が求められる…という形で第一章の終結にします。
当事者の事は自分の過去を振り返ればいくらでもかけますが、治療者側の事は中々わからないので、とても助かります。
改めて感じますが、あのameblo大騒動は見事なケーススタディですね。治療者がクリニック外/amebloという日本のSNSで精神分析を使用した事例として、教科書級です。
今日は第二章の「権力構造」です。ここにもS先生とのやりとり「スコットランド🏴インシデント」と、ジャストアンサーの猫山司先生とのやりとり「専門職にいる精神科医の立場をどうお考えですか?」というプロンプト解析をしてみるつもりです。
コーヒー入れて書き始めますね。
Foeh先生のおっしゃる通りです。
出会った瞬間に予後が決まります。
最初の夢や箱庭に全体が映し出されてしまうのですから恐るべし(^^♪
要するにこれまでどう生きてきたか(無意識)がそこにあるだけということだから、そこをなんとかしておく(教育分析)しかないのですよね。
分析を受ければ、自分の思考の癖がわかるし、教科書で習った1つ1つの言葉の意味するところが自分の言葉(身体感覚かな)で理解できるわけです。
なのでフロイト派もユング派も相当な時間をかけて分析を受けます。
クライエント(来談者)の気持ちも知らないわけではないのです。
多分普通のクライエントよりクライエント歴長いですから。
得て公🐒心理士資格とは次元の違い過ぎる話ですよね(^^♪
なんだか有意義そうな今回の論文の完成も楽しみです。