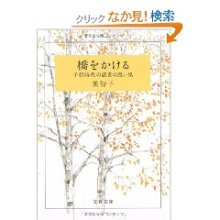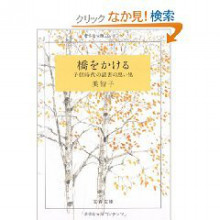『ゲド戦記』風に言うと、
『崖の上のポニョ』は
【真の名】
【わがまま】は
凡夫がつけた【あだ名】
【自己実現】しようとしている
ポニョやかぐやひめの
【真の名】が見えず
【わがまま】さんだと見做し、
【適応論】に閉じ込め
【適応障碍】や【発達障碍】として
【傾聴】し【ラポール】を形成するという
心理療法の定石すら守らないで
価値判断を押し付けて教育する
そんな失礼なことができる
心理療法家は
フジモトと同じです。
ただ…
フジモトは
最後に
改心しましたよ
「ジブリ『崖の上のポニョ』」カテゴリーアーカイブ
『崖の上のポニョ』の主人公宗介
『崖の上のポニョ』のヒロインは
ポニョですね。
ポニョちゃんはただのポニョちゃんではなく
【崖の上の】ポニョちゃんでしたね。
如人千尺懸崖上樹
↑ ↑
ポ ニョ 崖の上の
お坊さんでなくても
公案で【脳トレ】
しておくことが
生きるうえでの
【危機管理】になり
【こころのケア】になります。
なんせ
この国では
こころの病は
【自力】で治さなくてはならないのですから。
だから子どものころから
漫画『一休さん』
などを見て学習するのですね。
前置きが長くなりました。
宗介は主人公です。
主人公はヒロインを助けるのですね。
ですから
崖っぷちにいる人を助ける人は
宗介のようでなくてはなりません。
もしあなたのおかれた立場が
どうもポニョ的で
孤立無援である場合は
あなたのこころのなかに
宗介を育てる必要があります。
宗介はなぜ生まれたかというと…
宮崎駿監督がおっしゃるには
いわゆる【いい子】というのがあるけれど
どうも【いい子】ってのが問題だと思われたんですね。
(人のいいなりになったり、常識にとらわれたり、都合のいい子だったり…かな)
これは別に悪い子になれってわけではないのですが、
ではいい子でなくて
何なのか?
それは【まっすぐな子】です。
まっすぐというのは
【素直】ということで
これはフツーの日本語ですが、
案外【素直】な人は少なく
【素直】になるのは難しい。
そして【素直】にもしなれたら…
なんでもうまくいくのですね。
思えば勉強にしても習い事にしても
【素直】=上達の極意
だと言われています。
要するに【素直】は
ありふれてて見過ごしやすいけど
【魔法】のようなものだと思います。
監督は魔法が普通にあることを書きたかったんです。
ありもしないオカルト的なものではなくて
現実にある魔法です。
【素直】は日本語的です。
英語にありますか?
ストレートとは違うし
人の言いなりになることでもありません。
最近亡くなった土居健朗先生が
【素直】は実に日本的だと言っていました。
『人魚姫』にはない世界です。
公案を解いて
自己実現するには
【素直さ】が必要なのですね。
宮崎監督は
5歳の子を主人公にするのは
ある種の【冒険】だったとおっしゃいます。
それで物語が成り立つのかという一抹の不安ですね。
監督は冒険したのです。
今の心理療法は冒険させません。
教育して閉じ込めます。
(フジモトみたいです)

しかし結果として
大成功し、
5歳を主人公にしてよかったと
思われたそうです。
そしてわかったのは
①まっすぐであるには、貫いていかなければならない。
②貫いていくには、ハードルをいくつも越えていかなければならない。
③そのハードルは、見落としそうなハードルである。
④そのハードルをいかにも越えましたというのではなく、
自然に超えていく必要がある。
ということでした。
たとえば
宗介が最初にポニョを助けたとき
息を吹き返したポニョから
水をかけられました。
宗介は驚きますが、
すぐ笑っています。
保育所のクミコちゃんなどは
おなじ場面で泣いてしまいます。
おしゃれしてるのに
お洋服がぬらされてしまったからです。
自意識が強すぎるとだめなんですね。
あるいは
物語のクライマックスで
宗介は危機に見舞われます。
町が水没していて
避難所に向かうのですが、
ポニョと2人っきりです。
しかもポニョは瀕死で魚に戻りかけてるし
なんとも心もとない状況で
ポニョを連れ戻そうとする
お父さんのフジモトが
子どもだと思ってだましにかかります。
一方で
デイケアにきている【トキさん】が
「こっちに跳びな!」
と叫びます。
トキさんはちょっと偏屈なばあさんで
フジモトは一見紳士です。
おかあさんも一緒だからと言われてしまうと
ホロリとしついていきたくもなります。
しかし
宗介はトキさんの方へ跳んだんです。
危機一髪の瞬間に
自分の目で見て
自分の頭で判断して
トキさんを選んだんです。
(フジモトは今の心理療法を風刺してるかも)
そういう宗介の
【まっすぐさ】が
自分を救い、護り
結果として世間からも受け入れられるのだと思います。
【トキ】さんの意味についてはまた!

↑
これが【百尺竿頭】です!
もうだめだアと思うところから
さらに一歩進む。
これが極意です!
あきらめちゃダメ!
見えないものに橋をかける
美智子さまの御著書『橋をかける』のサブタイトルは…
『子供時代の読書の思い出』
一方『崖の上のポニョ』のパンフレットにある監督企画意図の最後は
こう結ばれています。
『少年と少女、愛と責任、海と生命、
これ等初源に属するものをためらわずに描いて、
神経症と不安の時代に立ち向かおうというものである。
宮崎 駿』
見えないものにも
橋は架かります。
それ(ラポート)は
奇跡を呼ぶ魔法でもあります。
監督企画意図にも書かれています。
『魔法が平然と姿を現す世界。
誰もが意識下深くに持つ内なる海と、
波立つ外なる海洋が通じ合う』
誰もが持つ無意識の世界での現実について描かれているのです。
特殊な人の特殊な話ではありません。
絵空事ではありません。
続きを読む
皇后美智子さま 『橋をかける』
皇后 美智子さまが
ご成婚50周年に
子どもたちの希望と平和のために
語られたお言葉 ―。
まっすぐな男と曲げられない女が基本
『崖の上のポニョ』は
5歳の少年宗介が、さかなの子ポニョと出会い、心を通わせる物語です。
5歳に何ができる?!と
思われるかもしれません。
しかし宗介がまっすぐさを貫くことが
ポニョのまっすぐさとリンクすると、
お母さんのリサや
デイケアセンターのおばあちゃんたちなど
周囲の人が変化し
応援してくれるようになりました。
それは嵐を呼ぶような大変化で
なんとポニョのお父さんフジモトまで改心させました。
まっすぐな【橋】が1つ架かると
いろんなものにつながり
それらの力も得ながら
大きく変化してゆけるのだと思います。
宗介ひとりの力ではないけど
宗介ひとりの力です。
最近のTVでも
『まっすぐな男』と
『曲げられない女』が
別のテレビ局で同時進行中です。
続きを読む
こころが通うと魔法が使えるようになる
『崖の上のポニョ』のストーリは…
海沿いの崖の上に住む5歳の少年宗介が、さかなの子ポニョと出会い、心を通わせる物語です。
ポニョは家出しようとしますが、一度は成功しても、すぐ父フジモトに海へと連れ戻されてしまったりして容易ではありません。でもあきらめないでいると、「魔法」が使えるようになって、願いが叶いました。
【ラポート(心を通わせる)】で【魔法】が使えるようになります。
魔法とは何か。
ブリュンヒルデという名前から、ポニョという名前に変わることです。
生まれ変わるんですね。
もちろんこの世で!
昔の日本人はよく名前を変えたようです。
子どもから大人になる時や襲名、僧籍に入るとき、あるいはそれを踏襲したのでしょうが、
茶道や華道、書道など【道】のつくようなお稽古事にもそれは見られます。
【翠雨】もそんな名前です。
【無我】っていうのはそういうことのようですね。
難しいことではなく、その場その場で生まれなおす。
それが本当に生きているということです。
一日のなかでも自分のことを
「私が」と呼んでいるかと思えば、
携帯に出るとたちまち「俺?」
家に帰ると「お父さんはねえ」
というように、ころころ変わります。
日本人特有ですね。
相手にあわせ、立場にあわせ、状況にあわせ…
なかなか凄い芸当です。
自分の誕生を祝福してくれ、名前をつけてくれた親には感謝するけれど、
そのときこめられた願い(第一の名前)だけで生きていくには
人生は長すぎる。
そして『崖の上のポニョ』って名前は【公案】でしたね。
魔法といってもありもしない魔法ではなく
難しいけど、答えのある問題を解くことなんです。
PTSDに罹患すると、お坊さんでなくても【公案】に取り組むようになります。
続きを読む
ポニョTVデビューの視聴率は29.8%
金曜ロードショー『崖の上の上のポニョ』のTVデビューの視聴率は29.8%だったそうです。
たくさんの人が見たんですね。
同日、政府が出した自殺予防対策緊急プランより、ポニョの緊急デビューのほうが、絶望する人々を引き止める力があると思います。
『崖の上のポニョ』のストーリは…
海沿いの崖の上に住む5歳の少年宗介が、さかなの子ポニョと出会い、心を通わせる物語です。
ポニョは家出しようとしますが、一度は成功しても、すぐ父フジモトに海へと連れ戻されてしまったりして容易ではありません。でもあきらめないでいると、「魔法」が使えるようになって、願いが叶いました。
変わりたいと思っている人にとって、心を通わせることのできる存在は貴重です。
心理学ではラポートと言います。心と心に橋をかけるんですね。
安心して思ったことが話せる関係を意味しています。
これがありそうでなかなかないのです。
PTSDに苦しむ人たちへの支援には宗介のような素直な存在が不可欠です。
要するに何も難しいことではなく、相手の言っていることを否認したり否定したり無視したりするのではなく【傾聴】することですから、実は5歳の子どもでもできることなんです。
続きを読む
見えないものに橋をかける
美智子さまの御著書『橋をかける』のサブタイトルは…
『子供時代の読書の思い出』
一方『崖の上のポニョ』のパンフレットにある監督企画意図の最後は
こう結ばれています。
『少年と少女、愛と責任、海と生命、
これ等初源に属するものをためらわずに描いて、
神経症と不安の時代に立ち向かおうというものである。
宮崎 駿』
見えないものにも
橋は架かります。
それ(ラポート)は
奇跡を呼ぶ魔法でもあります。
監督企画意図にも書かれています。
『魔法が平然と姿を現す世界。
誰もが意識下深くに持つ内なる海と、
波立つ外なる海洋が通じ合う』
誰もが持つ無意識の世界での現実について描かれているのです。
特殊な人の特殊な話ではありません。
絵空事ではありません。
皇后美智子さま 『橋をかける』
まっすぐな男と曲げられない女が基本
『崖の上のポニョ』は
5歳の少年宗介が、さかなの子ポニョと出会い、心を通わせる物語です。
5歳に何ができる?!と
思われるかもしれません。
しかし宗介がまっすぐさを貫くことが
ポニョのまっすぐさとリンクすると、
お母さんのリサや
デイケアセンターのおばあちゃんたちなど
周囲の人が変化し
応援してくれるようになりました。
それは嵐を呼ぶような大変化で
なんとポニョのお父さんフジモトまで改心させました。
まっすぐな【橋】が1つ架かると
いろんなものにつながり
それらの力も得ながら
大きく変化してゆけるのだと思います。
宗介ひとりの力ではないけど
宗介ひとりの力です。
最近のTVでも
『まっすぐな男』と
『曲げられない女』が
別のテレビ局で同時進行中です。