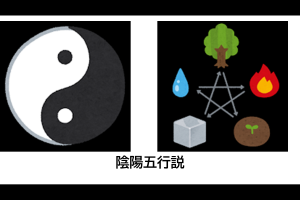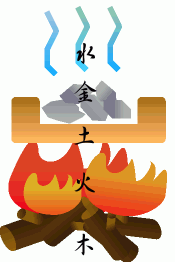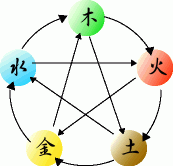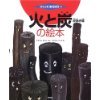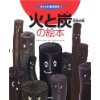利休忌が過ぎ
現代の茶道を完成させた茶聖
本日は隠元忌です。
日本でのお煎茶の開祖
江戸時代前期に渡来した
中国明代の禅僧で
アフリカでキリンを見せてあげると言うと
中国にもいるからいいよと言ったとか。
中華(世界の中心)の意味がよく伝わるepisodeです。
そういう国を相手にしているという意識の欠如は致命的かも
大事なときに出てくる麒麟ですね。
日本黄檗(おうばく)宗の開祖です。
故郷と同じ黄檗山萬福寺
源氏物語で知られるウジウジの辺境
宇治市に似合わない中国風で親しみのあるお寺☯
禅と言えば
臨済宗と曹洞宗で
最初は
臨済正宗と称していたけれども
双方に多大な影響を与えました。
もう一人の尽力者が
中国僧の道者超元とは奇遇
曹洞宗の開祖は中国帰りの道元
禅も一太極二陰陽の構図です。
まもなく
シルクロードの隠れた元が明らかに