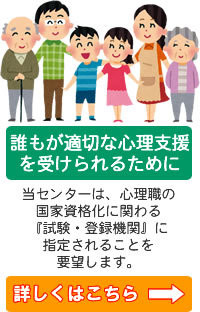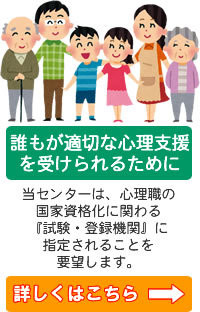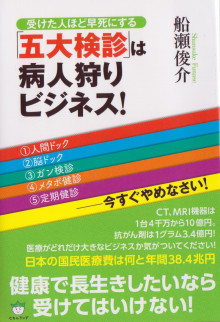15日
午後10時40分頃
自宅マンションで
同居していた男性(50)の腹部を包丁で刺して
殺害しようとした
16日になれば
別人のような解釈となり
「うっぷんがたまっていた。殺すつもりはなかった」
川崎市の女性調理師(43)が
直後にいつもの人格にもどり110番通報
現行犯逮捕されました。
調理師なのに包丁🔪とは
心身障害由来となると欠格次項になるのかな。
PTSD治療が成功しないと復職できませんね。
解離すると一番してはいけないことをするという
定義そのままです。
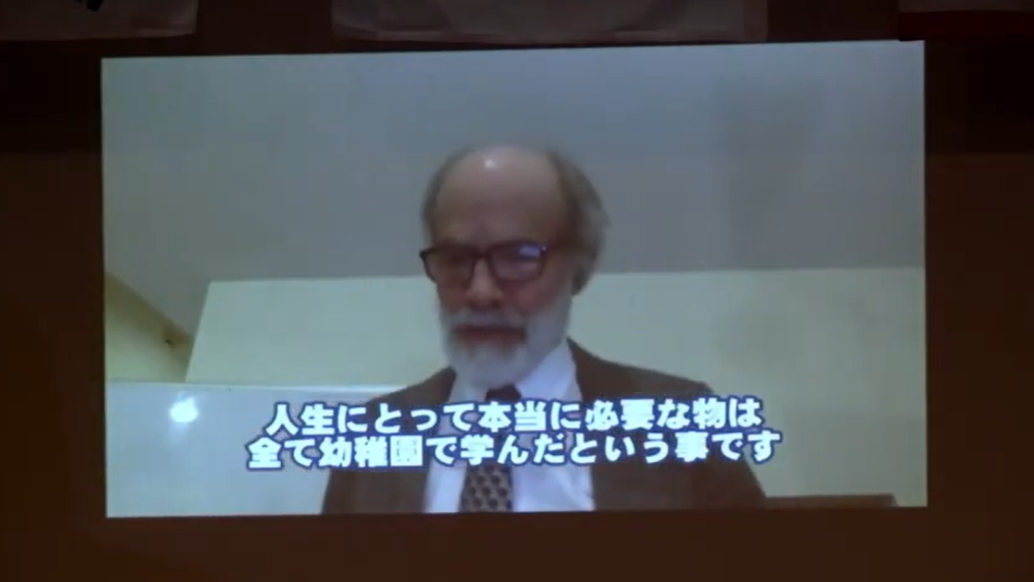
幼稚園で習ったはずですが
“Running with Scissors”・・・”ハサミを持って走る”は
危ないことをする時によく使われる比喩らしい。
![DMM.com [ハサミを持って突っ走る] DVDレンタル](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqG2iKk21yfwbEKmT7hy3xg0pSrc1Yz6TlnvOO2-0sxC9LWDbzJyzDgM6CJMVNZpLMRiAH6Bb-l5V9M2Xi7OLaOPrPey4iBq80rrHYXVJ_leE_YAqi9u3t9sFIjhUqwiqA7-IsG3dfERKx424Fh4_pq77A79FmFWexektPoWp92fecZz7HhJoBnUv-ooF8dwyTVLJxVnBYt4_9J5mpcWI7EBg=/n_606rdd40861rpl.jpg?errorImage=false)
ハサミを持って突っ走りたくなるような
主人公の少年の置かれた環境は悲惨
コメディなのに殆ど笑えず
どういう視座で見てよいのか戸惑う設定
身の上の人は少なくなく
登場人物がみな
苛立ち、恐れ、泣き叫びたいのを
必死に我慢して取り繕うことで
疲弊しきり
いつかスーパーマンが現れて現状がよくなることを願うものの
(期待の星 得て公🐒(別名公認心理師)は
いつ複雑性PTSD治療を
保険適応で標準のものとするのでしょう?)
状況はよくなったり再び悪くなったりを繰り返す。
精神病棟のようだという指摘もある。
母親は
精神分析医の治療を受けるほどです。
ヤブ医者で
入院食はドッグフードという虐待環境は
風刺ですね。

それらしく見えます。
恰好だけフロイト
結局スーパーマンは現れなかったけれど
現状は悲惨なまま
美容師になりたかった少年は
トラウマとハサミは使いよう
殺人者になるか自己実現するか野良患者になるか
作家になったそうです。
少年=著者
当事者研究ですね。