痛みには
いろんな原因があるようですが
窮極のところ…
病院に行ってもわからない。
ならば
病院では治らない。
ジブリの新作の少年の頭痛は
最初に書きますがこれこそが一般です。
ちょっと特殊です。

石で殴ったものなので
痛かったでしょうし
往診してもらい
おばあちゃんたちに看護してもらってもいますが
痛いとは一度も言わなくて
最後に
ジブリワールドの旅のあと
「この傷は自分でつけました。
僕の悪意の印です」と言いました。
自傷行為はしかたなくしてしまうものなので
解離行動
魂の方が痛いのでスッとする。
― 病院で治らないモノが治るように感じる。
― ― ある種の魔法
ブロック注射より効くので依存症になる。
自傷行為を繰り返す人が罪人というわけではないですが
でもこじらせると…
ベンゾ地獄のように逃げ場がない…
これが言えるまでの物語なので ⇒ 傷が癒える
『君たちはどう生きるか』について
自分なりに納得できる答えをつかみ
自分と世界を肯定できる意志が生まれた。
石はきっかけとして無意識が投げたもの。
― 心的外傷を墓標に閉じ込めることは実は相当な罪悪
目にはみえないけど
常識にまぎれて悪意に見えない。
自己実現を阻害する
不思議に答えがある。
― 思議できない。
― ― 常識・論理の外のはなし
悪いもののことなのでしょう。
影(シャドウ)のアオサギも
誰のこころにもあるものですよ。
醜いうそつき詐欺師のように描かれているし

糞だらけのインコや
正法眼蔵@道元 は人間のことを臭皮袋と書いている。
無個性で天才を殺害しようとする烏合の衆
おばあちゃんも欲張りで
(物のない時代なので)煙草や缶詰で簡単にネゴシエーション
子どもといえばいじめっ子みたいな
毛色の違う子は即集団いじめ
悪意がことさら強調されて
人類はそこまで悪くないです💦
表現されています。
純粋経験に対する悪なのでしょう。

善 = 自己実現
君たちはどう生きるか⁉
個性化の過程@自己実現 を生きる。
純粋経験とは何か⁉
それは少年が経験した
『十牛図』のような地下世界でしょう。
アニメでしか描けない。
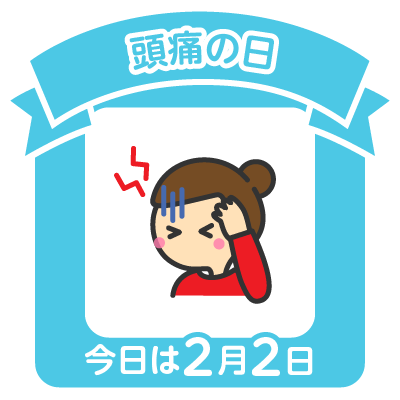






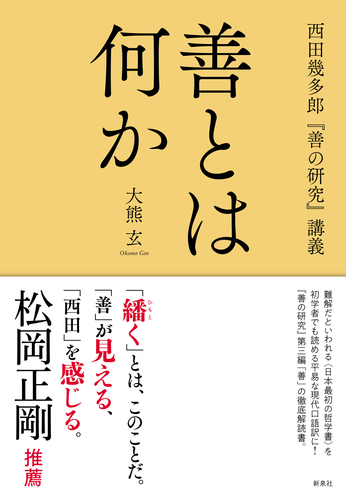
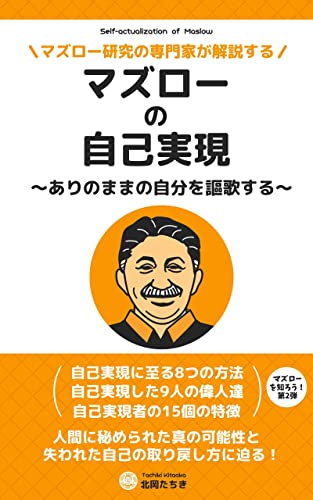
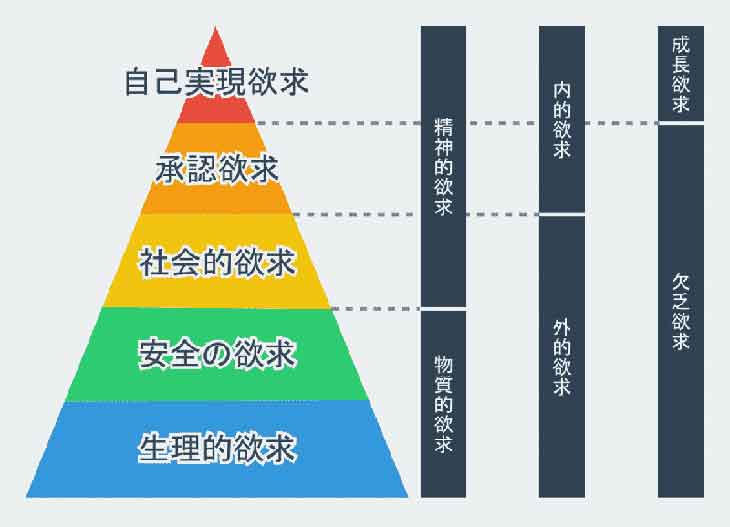
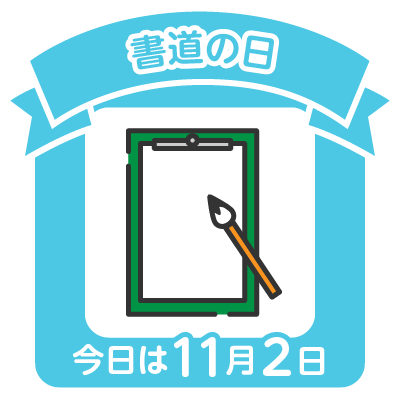




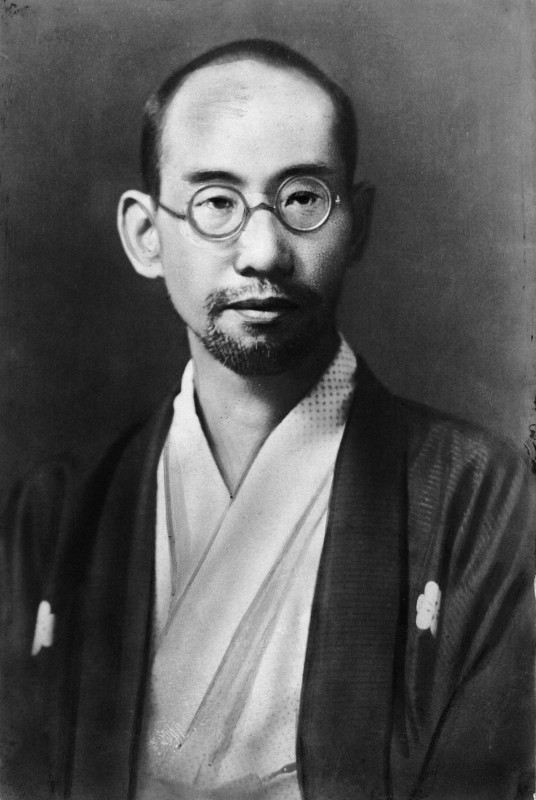


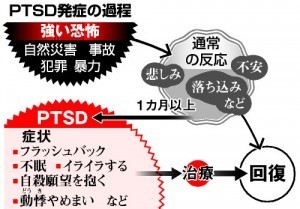






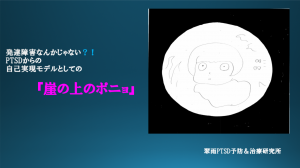









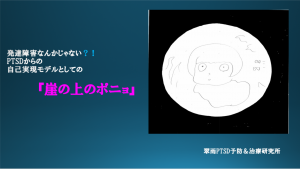

 動☯静
動☯静






















 大人の発達障害?
大人の発達障害?





